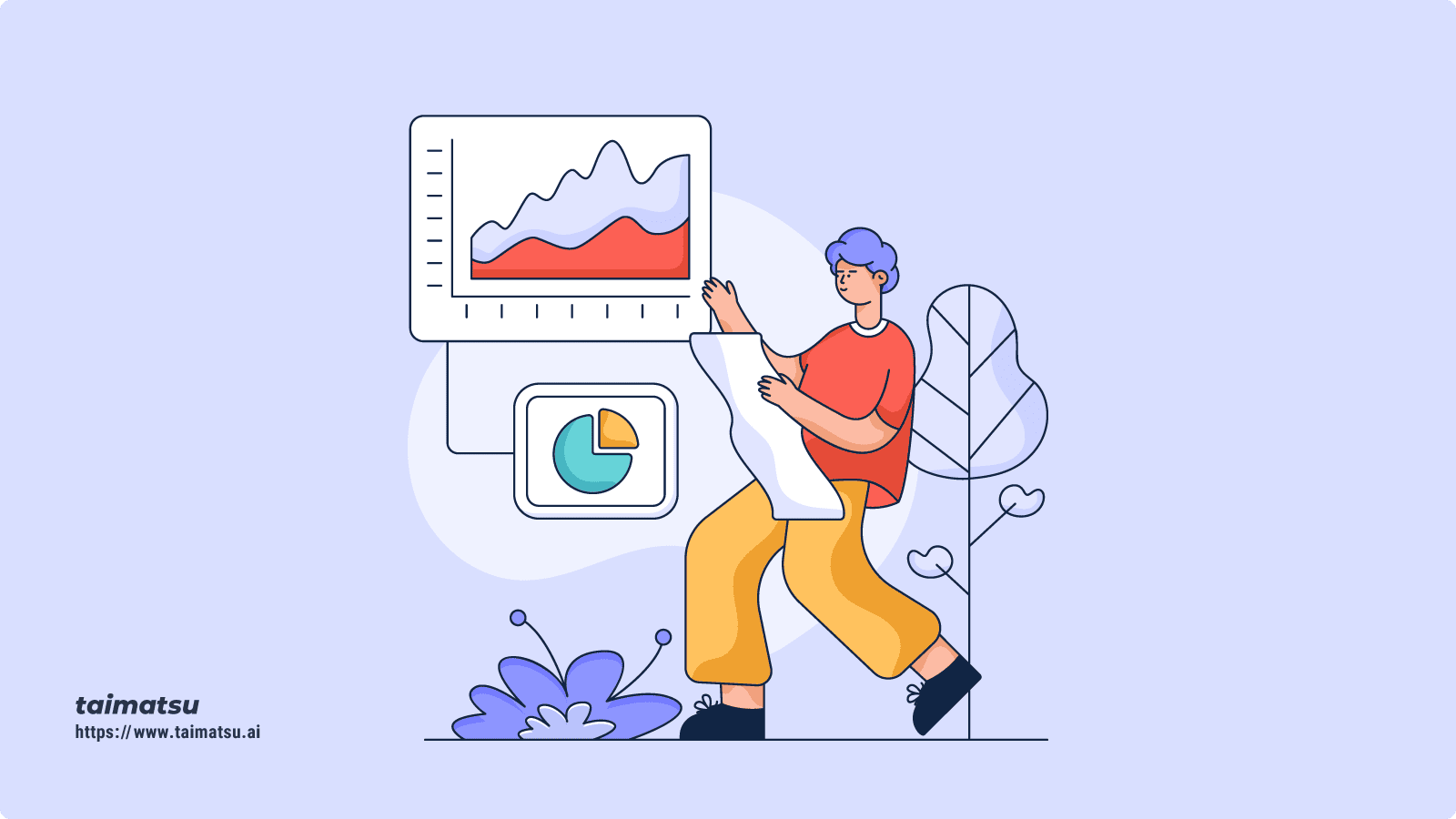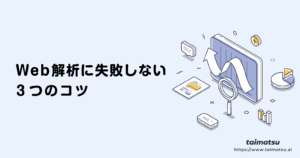Google Analyticsを活用する上で、これだけは覚えておきたい分析指標を解説します。
Google Analyticsに、どんな分析指標で解析できるか知っておくことで、改善施策も作りやすくなります。
サイトへの訪問数を調べる(ユーザー / セッション)
サイトへの訪問数を知るための指標は、「ユーザー指標」と「セッション指標」の2つです。
この2つは「訪問数」を集計する指標ですが、明確な違いがあります。
ユーザー指標
同一人物が何度訪問してもカウントは増えない
ユーザー指標は、同一人物なら複数回訪問しても1回とカウントします。
例えば、Aさんが10回訪問し、Bさんが5回訪問した場合、合計15回の訪問があったことになりますが、ユーザー数は2です。
ユーザー指標は、「どれだけサイトに訪問があったか?」ではなく、「どれだけ様々な人からサイトに訪問があったか?」を見る指標になります。
セッション指標
同一人物が訪問する度にカウントが増える
セッション指標は、同一人物の複数回の訪問をその都度カウントします。
例えば、Aさんが10回訪問し、Bさんが5回訪問した場合、ユーザー数は2ですが、セッションは合計訪問数の15です。
【注意】集計単位によって、ユーザー数は変化する
日ごとの集計の場合
日ごとにユーザー数を集計した場合、同一人物であっても翌日に訪問した場合は、新しくカウントされます。
同一人物として複数回の訪問が省かれるのは、1日単位(=集計単位)ということです。
月ごとの集計の場合
月ごとにユーザー数を集計した場合、同一人物であっても翌月に訪問した場合は、新しくカウントされます。
同一人物として複数回の訪問が省かれるのは、月単位(=集計単位)ということです。
注意
集計単位で同一人物の訪問数の重複が省かれるため、日単位のユーザー数を足してその月のユーザー数を算出しても、月ごとのユーザー数とは異なります。Googleアナリティクスの「集計期間」で重複を省いたユーザー数になることをご注意ください。
サイトの定着状況を調べる(新規ユーザー / リピーター)
新規ユーザーとリピーターの違い
サイトにやってくるユーザーが初めての訪問の場合を「新規ユーザー」、2回目以降の場合を「リピーター」として集客されます。
活用方法
訪問者が「新規ユーザー」か「リピーター」かによって、取るべき集客施策は大きく変わります。
新規ユーザーを増やしたい場合は、まずサイトの存在を知ってもらうことが重要です。
そのために、Web広告の出稿、展示会への出展、SEOやLLMOの強化に加えて、SNSでの情報発信やキャンペーン展開 などが有効です。幅広いチャネルを使って接点を増やすことが、新しいユーザーの獲得につながります。
リピーターを増やしたい場合は、一度訪問した人が「また来たい」と思える工夫が必要です。
例えば、会員向けメールマガジンの改善、再訪問したくなるようなコンテンツ更新、リピーター限定のクーポン配布やポイント制度、さらにSNSでのコミュニティ運営やフォロワー限定情報の発信などが効果的です。
このように、単に訪問数を見るだけでなく、それが新規ユーザーなのかリピーターなのかを切り分けて分析することで、どの集客施策を優先すべきかを正しく判断できるようになります。
新規ユーザーとリピーターを判別する方法
Cookie(クッキー)で、判別する
ユーザーがサイトを訪問すると、GoogleアナリティクスはCookie(クッキー)を発行し、ユーザーのブラウザに保存します。次回以降の訪問時には、このCookieを参照することで、訪問ユーザーが初めての訪問者(新規ユーザー)か、過去に訪問したことのあるリピーターかを判断します。
Cookie(クッキー)は、インターネットを利用するときに、Webサイトからあなたのパソコンやスマホのブラウザに一時的に保存される「小さなメモ」のようなものです。
例えば、ネットショップでログインしたり、カートに商品を入れたりしたとき、その情報をCookieに記録しておくことで、次に同じサイトを訪れたときにログインを省略できたり、カートの中身がそのまま残っていたりします。
つまり、Cookieは「前回のあなたの利用状況を覚えておく仕組み」で、便利にインターネットを使うために活用されています。
リピーターでも「新規ユーザー」として集計される3つのケース
Google Analyticsでは、Cookieを活用して「新規ユーザー」と「リピーター」を識別していますが、ブラウザや時間の経過により、正確に識別できないケースがあります。以下にそのケースをご紹介します。
① Cookieを削除した場合
Cookie(クッキー)は、ブラウザに保存されますが、ブラウザの設定からユーザーが自由に削除することもできます。その場合は、過去に訪問していたとしてもその情報が削除されているため、リピーターではなく、「新規ユーザー」として集計されます。
② 同一人物でも異なるブラウザでアクセスした場合
Cookie(クッキー)は、ブラウザごとに保存されるため、同一人物であっても別のブラウザで同じページにアクセスした場合は、それぞれ「新規ユーザー」として集計されます。
③ 一定期間、訪問がない場合
Google Analyticsの初期設定では、前回の訪問から2年以上経過すると、「新規ユーザー」としてカウントされます。
ページの閲覧数を調べる(PV:ページビュー)
PV(ページビュー)とは、インターネットを通じてブラウザにページが表示された回数です。
注意点としては、「PVはページを見た人数ではない」ことです。
同一人物が、ブラウザの「更新」ボタンをクリックしてページを再表示した場合、PVは「2」とカウントされます。
同様にブラウザの「戻る」ボタンをクリックしてページが表示された場合もカウント対象となります。
- 一覧ページを表示
- 更新ボタンをクリックし、一覧ページを再表示
- 詳細ボタンをクリックし、詳細ページを開く
- 詳細ページで、戻るボタンをクリックし、一覧ページの戻る
この場合、一覧ページのPVは「3」です。
人気のあるページを調べる(アクティブユーザー)
アクティブユーザーとは?
Google Analytics 4 の「アクティブユーザー」とは、単にサイトを訪れた人ではなく、一定の行動(エンゲージメント)をしたユーザー のことです。単純にページが閲覧されただけではなく、「ちゃんと見てくれた人」の数を把握できる指標です。
ユーザーが以下のいずれかを満たした場合、アクティブユーザーとしてカウントされます。
- 初回訪問(first_visit イベント)
- アプリを初回起動した(first_open イベント)
- エンゲージメントが発生した(以下のいずれか)
- サイトやアプリを10秒以上利用した
- 2ページ以上閲覧した
- コンバージョンイベント(例:問い合わせ送信、購入完了など)を発生させた
■ 初めてサイトに訪問し、ページAを1秒だけ見て閉じた
| ユーザー | カウント1 |
|---|---|
| アクティブユーザー | カウント1 ← first_viewイベントが発生するため |
■ 再びサイトに訪問し、ページAを1秒だけ見て閉じた
| ユーザー | カウント1 |
|---|---|
| アクティブユーザー | カウント0 ← first_viewイベントは発生しないため |
- 新規訪問者:
必ず「アクティブユーザー」にカウントされる(直帰したとしても) - 再訪問者:
エンゲージメントが発生しないと「アクティブユーザー」にカウントされない
ページAを15秒間、閲覧して離脱
| ユーザー | カウント1 |
|---|---|
| アクティブユーザー | カウント1 |
- 1ページで離脱しても、10秒以上の滞在時間があれば、アクティブユーザーとしてカウントされる
ページA → ページBと遷移(合計5秒)
| ユーザー | カウント1 |
|---|---|
| アクティブユーザー | カウント1 |
- 2ページ以上閲覧した場合は、時間に関わらず、「アクティブユーザー」としてカウントされる
- ページAとページBの両方とも「アクティブユーザー1」としてカウントされる
商品購入、アカウント登録、お問い合わせを行った
| ユーザー | カウント1 |
|---|---|
| アクティブユーザー | カウント1 |
- 時間やページ数に関わらず、CVしたらアクティブユーザーとしてカウントされる
活用方法
表示されるたびに報酬を得られる広告をサイトに掲載している場合は、同一人物かどうかは関係なく、PV(ページの表示回数)が増やす施策が必要です。
一方で、商品ページの場合はPV(ページの表示回数)よりも、同一人物の複数回の表示回数を省く「アクティブユーザー数」が重要な指標になります。
例えば、特定のページを1人のユーザーが1,000回みた場合(ユーザー1、PV1,000)よりも、500人のユーザーが2回みた場合(ユーザー500、PV1,000)の方が、同じPVでありながら様々のユーザーを集客できているページといえます。
このようにサイトやページの目的にあわせて、見るべき指標を使い分けることが大切です。
ページが読み込まれているかを調べる(平均エンゲージメント時間)
ページ内のコンテンツがちゃんと読み込まれているかを調査する方法として、「ページが何秒見られたか」と「ページをどこまでスクロールしたか」の2つ指標があります。
平均エンゲージメント時間
Google Analyticsでは、平均エンゲージメント時間(アクティブユーザー当たりの平均エンゲージメント時間)という指標で、そのページが平均何秒見られたかを集計します。
落とし穴
実は、平均エンゲージメント時間だけでは、ページを評価できません。
複数のページを評価する際、「平均エンゲージメント時間」が長いページがより多く読み込まれていると評価してしまいがちですが、ページを評価するには「平均エンゲージメント時間」の指標だけでは不十分です。
例
例えば、以下のページAとBのどちらがユーザーに読み込まれているか評価する場合、「平均エンゲージメント時間」だけで判断すると、ユーザーに読み込まれているのは「ページB」と言えます。
| ページA | ページB | |
|---|---|---|
| 平均エンゲージメント時間 | 5分 | 10分 |
| コンテンツを読了するために必要な時間 | 5分 | 30分 |
しかし、「ページA」と「ページB」のコンテンツ量が違う場合はどうでしょうか?
平均エンゲージメント時間に加えて、コンテンツを読了するために必要な時間も鑑みると、読了するのに30分かかる「ページB」の平均エンゲージメント時間が10分ということは最後まで読んでいない人が多いことになります。
一方で、読了するのに10分かかる「ページA」の平均エンゲージメント時間は10分のため、多くの人がページを最後まで読んでいる可能性が高くなります。
この例のように「平均エンゲージメント時間」のみでページの評価をすると誤った評価をしてしまう可能性があり、注意が必要です。
さらに「ページA」については、コンテンツを読了するために必要な時間と平均エンゲージメント時間が同じであっても、実際にページの最後まで読んでいるかはわかりません。途中で理解が困難なページがあってページの最後まで辿り着かずに5分経過して離脱している場合もあります。
そこで、Google Analyticsにはページがどこまでスクロールされたかがわかる「スクロール」という指標があります。
ページが読み込まれているかを調べる(スクロール)
Google Analyticsの指標には「_scroll」というイベントがあります。このイベントはそのページに訪問したユーザーがページの下部(垂直方向に90%下)までスクロールした際にカウントされるイベントです。
「どれほどのユーザーがページ下までスクロールしたか」の情報は、コンテンツをどれほど読み込まれたのかを評価する指標として使えます。
スクロール数
- ページの下部90%地点まで到達した時点で「_scroll」イベントが1回発生する
- ページを読む途中(例:30%や50%地点)ではイベントは発火しない
- スクロール数は、その地点に到達した「ユーザー数」を指す
- ほぼ最後までページを見たかどうかを測るためのイベントとして使える
例1
例えば、ページに100人が訪問したとします。
そのうち 40人がページの下90%地点まで到達した場合、スクロールイベント数は 40 になります。
例2
同じ日に同じページにユーザーAが4回アクセスし、以下の行動をとった場合のスクロール数は「1」です。
- 1回目のページアクセスで、ユーザーAが、ページの下部90%地点で離脱
- 2回目のページアクセスで、ユーザーAが、ページの下部50%地点で離脱
- 3回目のページアクセスで、ユーザーAが、ページの下部10%地点で離脱
- 4回目のページアクセスで、ユーザーAが、ページの下部95%地点で離脱
1ユーザーが、 1ページにつき、スクロール90%達成した時点で、スクロール数は1回だけカウントされます。
その後同じページを再訪しても、同じユーザーであれば 追加でカウントされません。
① ページAをユーザーAが1回目表示 → 90%到達
_scrollイベント発生 → 1回カウント- ページAの「スクロール数」=1
- ページAの「スクロール到達ユーザー数」=1
② ページAをユーザーAが2回目表示 → 50%到達
- 90%未満なので
_scrollイベントは発火せず - すでに①で発火済みなので、追加カウントなし
- ページAの「スクロール数」=変わらず1
③ ページAをユーザーAが3回目表示 → 10%到達
- 90%未満なので
_scrollイベントは発火せず - 追加カウントなし
- ページAの「スクロール数」=変わらず1
④ ページAをユーザーAが3回目表示 → 95%到達
- すでに①で「90%到達済み」なので、新規の
_scrollイベントは発火しない - 追加カウントなし
- ページAの「スクロール数」=変わらず1
ユーザーAがページAを何度見ても、最初に90%に到達したときだけ「スクロール数=1」 と記録される。
2回目以降に、90%未満のスクロールがあっても「スクロール数」は、減算されません。
2回目以降に、90%以上のスクロールがあっても「スクロール数」は、加算されません。
注意点
ユーザーが 記事を熟読して下までスクロールした場合 でも、ユーザーが 開いてすぐに一気に最下部までスクロールした場合 でも、どちらも「_scroll = 1」と記録されます。
つまり、スクロールイベントが「1」だからといって必ずしもページの上から下まで熟読しながら読み進められたという意味ではないところは注意が必要です。
もし、そのような解析をしたい場合は、ヒートマップツールを活用することで、ページがどこまでスクロールされたか、ページのどの部分を熟読されたか、ページのどのボタンをクリックしたかを視覚的に解析できます。
おすすめのヒートマップツールは、ミエルカヒートマップ と Microsoft Clarity です。
エンゲージメント率
訪問経路と入口ページ(ランディングページ)との相性を評価する指標に、エンゲージメント率があります。
エンゲージメント率 = エンゲージのあったセンション数 ÷ セッション数 × 100
エンゲージのあったセッション数の定義は、以下のいずれかの条件に該当したセッションをカウントします。
3つの条件のうち、いずれかを満たすセッション
- サイト訪問後、10秒以上経過
- ページを2ページ以上閲覧
- キーイベント(コンバージョン)が発生
例
エンゲージメント率は、サイト内のページ移動ではなく、広告などの訪問経路からサイトにランディングしたときのページを対象に評価する指標です。
訪問経路・・・・Google広告、SNS、検索、外部サイトなどのこと
入口ページ・・・訪問経路から最初にランディングしたページのこと
訪問者が期待するコンテンツがランディングページにあれば、離脱せずにコンバージョンしたり、10秒以上かけて読み込んだりするため、その「訪問経路」と「入口ページ」は、エンゲージメントが高いという判断をします。
離脱率
離脱率とは、あるページが セッションの最後に見られた割合 を示す指標です。
ページ単位で算出され、「このページを最後にサイトを離れたセッションがどのくらいあるか」を把握できます。
Google Analytics4では、離脱率の指標は用意されておらず、自分で計算する必要があります。
ページAからページBにページ遷移したユーザーによって100PVあり、そのうち30セッションがページBを最後に離脱したとします。その場合の離脱率は、30÷100×100% = 30%です。
離脱率 = そのページを最後に見て離脱したセッション数 ÷ そのページの合計PV数 × 100
- 離脱は「そのページビューが最後だったかどうか」で判定されるため、分母は「セッション数」ではなく「ページビュー数」になります。
離脱率が高いからと言って、ユーザーの満足度が低い、低品質なページという評価は短絡的すぎます。その観点からもGoogle Analtyics4では、離脱率を標準のレポート機能から無くなりました。「探索」機能を使って算出もできますが、「レポート」機能からなくなったことからもGoogleとしては重要視していない指標だということが予想できます。
直帰率
直帰率とは、そのセッションが「入口ページ1ページだけで終了」した割合です。
つまり、ユーザーがサイトに来て、最初のページ(入口ページ)を1ページだけ見て離脱した場合を直帰とみなします。
旧バージョンのGoogle Analytics「ユニバーサルアナリティスク」では、「直帰率」という指標がありました。
訪問経路と入口ページ(ランディングページ)との相性を評価する指標として使われていましたが、新しいバージョンのGoogle Analytics4では、以下の計算式になります。
直帰率 = 100% ー エンゲージメント率
つまり、「直帰率」は「エンゲージメント率」を反転した指標ということです。
なぜ、算出方法が変わったのか?
たとえば、以下のユーザーを同等に評価して良いかというと、そうではありませんよね?
- サイトの訪問直後に直帰したユーザー
- サイト訪問後、しっかり時間をかけてコンテンツを読んで直帰したユーザー
旧バージョンのGoogle Analtyicsでは両者を「直帰したユーザー」として評価していましたが、しっかり時間をかけたユーザーは内容に満足して直帰した可能性があります。
そのため、直帰率をエンゲージメント率の反転した指標と定義した方が、納得感があります。
訪問経路(チャネル)
サイトへの訪問経路は、Google検索、広告、SNS、Emailなど様々です。サイト運営者としては、現状の改善や施策の評価をするために訪問経路を知ることは重要なポイントです。Google Analytics4 では、訪問経路ごとに特有の呼称があり、総称して「チャネル」と呼びます。
| チャネル名 | チャネルの意味 | 計測設定 |
|---|---|---|
| Organic Search | オーガニック検索からの訪問 | 設定不要で計測される |
| Referral | [Organic Search] や [Social] に分類されない訪問が分類されます。 例えば、ニュースサイトや個人のブログサイトなどの自社サイトとは別のサイトからの訪問など | |
| Organic Social | ソーシャルメディアからの訪問 例えば、X(Twitter)、instagram、Facebookなどからの訪問 | |
| Direct | 参照元のページが不明な場合に分類されます。 例えば、ブラウザの「お気に入り」からの訪問や、サイトのURLをブラウザのアドレスバーに直打ちした訪問など | |
| Paid Search | 検索連動型広告からの訪問 | 広告パラメータの設定が必要 |
| Affiliates | アフィリエイトサイトからの訪問 | |
| Display | ディスプレイ広告からの訪問 | |
| Paid Social | ソーシャルメディアでの有料広告からの訪問 | |
| Video | ビデオ広告からの訪問(YouTubeなど) | |
| メールからの訪問 | ||
| unassigned | チャネルルールにない訪問履歴が分類される |
計測設定が必要なチャネルで、設定しなかった場合
Paid Search
検索連動型広告(リスティング広告)からの訪問を分類するチャネルの [ Paid Search ] は、計測設定をしなかった場合、[ Organic Search ] に分類されてしまいます。
広告を運用する場合は、 SEOと分けて分析したいため、必ず計測設定はするようにしてください。
Affiliates
アフィリエイトサイトからの訪問を分類する [ Affiliates ] は、計測設定をしなかった場合は、[ Referral ] に分類されてます。 A8 や もしも などの大手アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)の管理画面からコピぺで使えるアフィリエイトリンクには計測設定がされているので心配いりませんが、会社が独自で運営しているアフィリエイトサービスの場合は、必ず確認をしておきましょう。
会員に配信しているメールマガジンからどのぐらいサイトに流入があったかを測定するには、メールマガジンからの訪問が [ Email ] に分類されるように計測設定が必要です。
計測設定をしていない場合、[ Direct ] に分類されます。
メールソフトがデスクトップアプリかWebサービスかによって、分類されるチャネルは下記のように変わります。
| パソコンにインストールして使うデスクトップアプリの場合 | [ Direct ] に分類される |
|---|---|
| Gmail や Yahoo!メールなどのWebサービスの場合 | [ Referral ] に分類される |
しかし、実際には、Webサービスのメーラーも [ Direct ] に分類されることが多いようです。